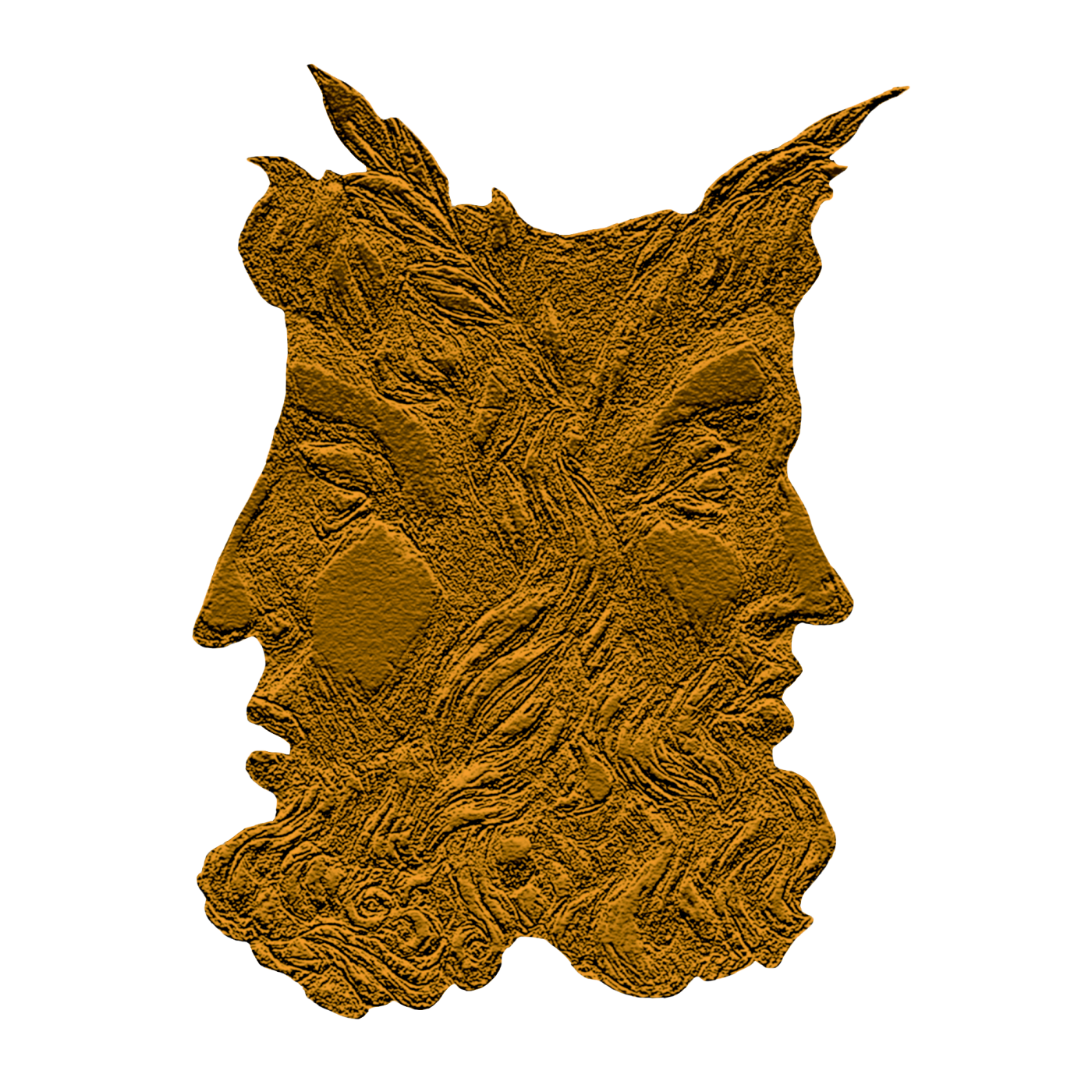|
2025/5/6
|
|
伴奏者に知っておいて欲しいこと |
|
|
今回、バーゼル国際歌曲コンクール2025 ファイナルを東京オペラシティ リサイタルホールにて開催し、ピアノ伴奏法について深く考えさせられました。 一流の審査員の先生方にとって、歌曲芸術の伴奏法にはこだわりがあります。それは今始まったこだわりではなく、歌曲芸術の伴奏法において誰もが知っておいて欲しいことです。 今回、ピアニストの伴奏の音量や音の響きについて、様々なコメントを実行委員会にて分析いたしました。歌い手を生かすのは伴奏者の役目であることと、一緒に物語を作り、語ること...歌曲において求められます。 ピアノの音量が大きいと...指摘を受けた方々において、その音量をすぐに小さくして明日からすぐに直るか...と言われると難しい問題です。 仮に音楽のスタイルや作品分析ができていても、演奏に反映されなければ良いピアノ伴奏者とは言えません。 音量が大きい....方は、ほとんど指先と鍵盤の物理的な距離感に囚われていることが多く、音を鳴らす時に、ピアノの弦、ホールの響き、歌い手の声量バランスを察知して音楽を構築していかなければなりません。 これを体現できるピアニストは体の核となる軸から手の指先をとおり、弦を鳴らす鍵盤の感覚をミリ単位で調整できる方であると思っております。そこには機械的な体の解剖学では留まらず、音を乗せる際に作品に込められたスピリットをお客様へ運ぶように演奏する...理想とされます。 YouTubeで今では簡単になんでも検索できる時代ですが、まずは最初に自分と楽譜だけで対話してみましょう。最初は難しくても、どんな風にピアノ伴奏が作曲されて歌のメロディーが乗せられているのか、音からまずは捉えてみましょう。今度は楽譜を外して、詩人の書いたポエムにインスパイアしてみましょう。その後、もう一度楽譜を見て、もともと詩人が書いた韻、リズムを踏んで作曲されているのか、もしくは音楽を優先して、言葉は後回しにされているのか観察してください。 音を奏でるにはColors, Farbenいくつもの音色があって、作曲家によっても音色の特徴があります。音圧も作曲家によって異なり、声を出すにあたっても、音圧を理解し発語すると、より作品ごとによって音楽の特徴が表に出るようになるでしょう。 またpianoやforteとは何の表記であるのか、作曲家はただ単に物理的に音を大きく、小さくとは指示していません。 pianoの音...その音色は幸福か、悲しみか、希望か、それとも祈りの音であるのか、 またforteの音...その音色は喜びか、期待か、怒りか、失望か、恐怖か... 音楽は人間の感情を表現できることもあれば、その反対に無の世界を表現することもできます。 これからもピアノ伴奏者には、より深く音楽を学んでいただき、歌手と一緒に音を創ることの喜びを感じて欲しいです。 |
|
| |