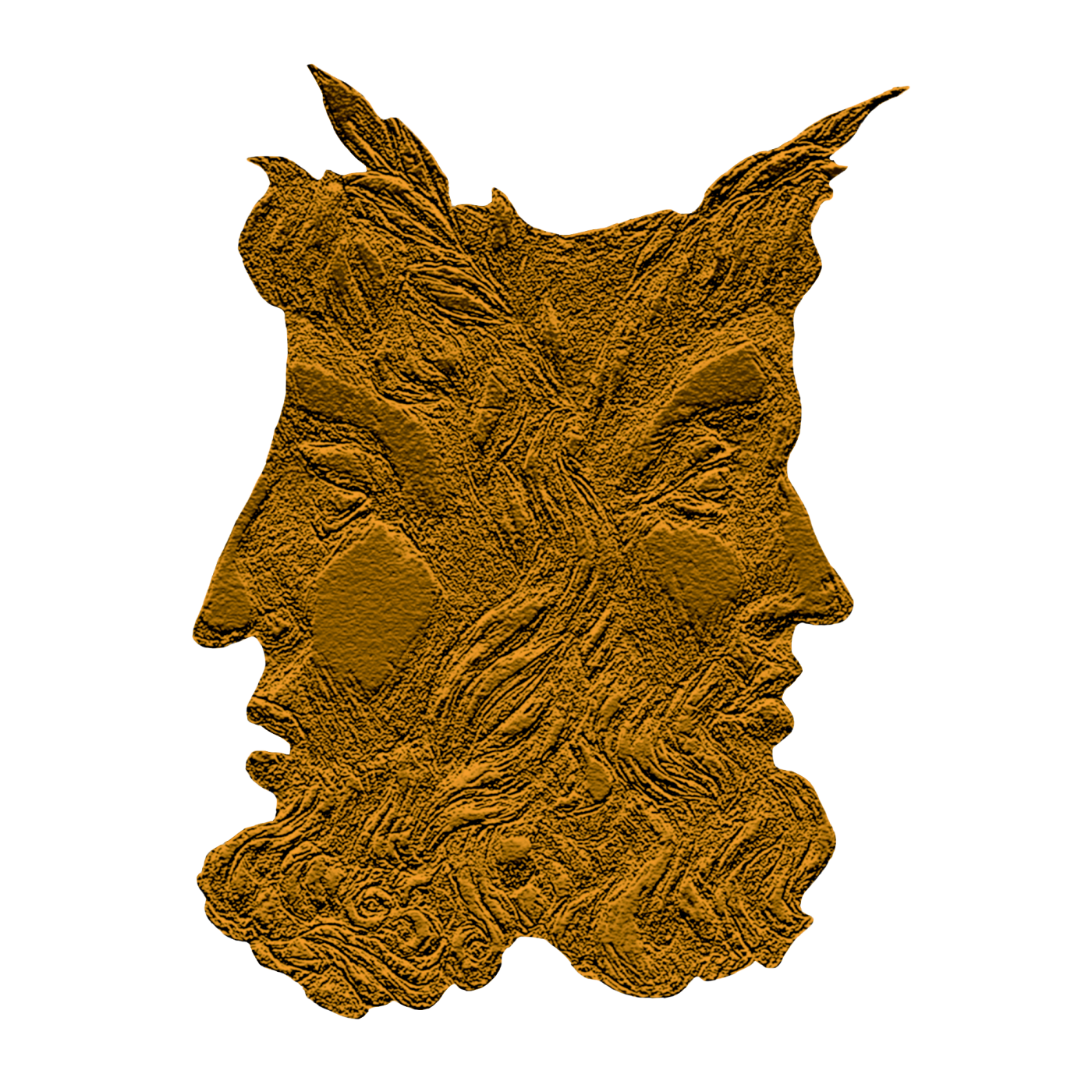|
2021/1/25
|
|
舞台語発音法の重要性について |
|
|
ヨーロッパの名だたる宮廷歌手から徹底的に指導を受けた経験の中で、日本にいた頃と遥かに感覚の相違があったのは、発音の感覚について。まだ、日本にいた頃にドイツ語は他の学生よりも多く触れていたせいか、そこまでの相違があるだろうとは想像もしていませんでした。 実際にドイツレパートリーを研鑽する中で、最初の頃指摘された事は『まだ東洋人の発語の仕方であり、アクセントの付け方など完全ではない』と。音楽解釈や発語に関して言えば、忘れらない恩師はテノールのSiegfried Jerusalem師匠とメゾソプラノのDonna Morein先生。東洋人の癖を熟知しており、実際に舞台でよく聴いた東洋人の発語の癖や、アクセントの位置、舌の位置、上下唇の使い方、口の開け方から、気が遠くなるほど細かく細かく、指導頂いた。振り返ると、厳しくも温かい恩師のお陰で『バイロイト音楽祭』のスカラシップに選ばれた事は、今も忘れられない思い出です。5人中、日本人は一人だけ、あとはドイツ人が3名、韓国人が一名。皆劇場の専属歌手で、さらに大きな劇場で歌うキャリアアップの為に、バイロイトに来ていました。ドイツのプレスでの評価を得たのも、気が遠くなるほど、打ち込んだ事が報われた瞬間でした。 日本に帰国後、指導者となり指導するようになって、感じる事があります。 1時間や45分の短いレッスンでは、私が経験した徹底的な発語のレッスンには、徹底的には時間をかけられないことを。そこで、ある時から発語とレパートリー、呼吸・発声学と分けて指導するようになってから、生徒さんの向上が一段と早くなりました。 生徒さんから実際に話を伺うと、ドイツ語も詩の解釈なども語学を学んだ年数や経験値によって、差が出てしまうことに気付きました。どの言語もそうですが、まずはテキスト詩の内容から入り、どのよう状況で詩を書いて、また作曲する経緯に至ったのか・・・じっくりと考えることに時間を使えば使うほど、深みが増してきます。 またレッスンではなるべく多くドイツ語で捉えて頂けるような工夫もしています。 日本語に訳してしまうと、ドイツ語本来の感覚と離れてしまうからです。 緊急事態宣言が出てまだ解除はされておりませんが、学ぶ事は継続できます。 目標に向けて、練習していきましょう。  2018 Rahmen der Bad Urach Herbst Musiktage mit Prof. Siegfried Jerusalem  2016 Rahmen der Bayreuter Festspiel beim Meisterkurs mit Prof. Siegfried Jerusalem  2015 in Hamburg mit Dirigenten Mathias Husmann  2017 in Wien mit Kammersaengerin Vesselina Kasarova  2019 in Rumaenien mit Pianisten Costin Filipoiu
|
|
| |